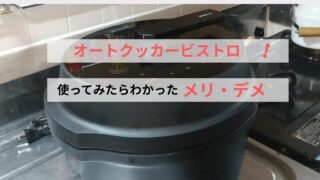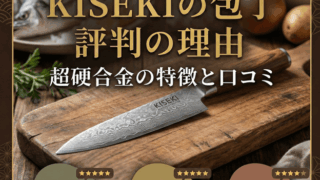木のまな板は、その温もりある質感と包丁へのやさしさから、多くの方に愛用されています。
しかし、大切に使っている木のまな板に、いつの間にかカビや黒ずみが現れてしまうと、気が滅入ってしまいますよね。
カビは見た目が不衛生なだけでなく、食材への二次汚染や健康への影響も懸念されます。
適切なお手入れを怠ると、せっかくの木のまな板も台無しになってしまいますし、最悪の場合は、買い替えを考えるしかなくなってしまうかもしれません。
一方で、木のまな板は正しくお手入れをすれば、長く清潔に使い続けられる優れた調理道具です。
この記事では、以下の具体的な解決策を順を追ってご説明します。
- なぜカビが発生するのか
- 重曹やクエン酸を使ったカビの落とし方
- ご自身でまな板を削る方法とホームセンターで依頼できること
- ハイター使用の危険性や変色のリスクといった注意点
- おすすめの除菌スプレー
- そして日々の手入れにオイルを活用する方法
- 無印やニトリといった身近なブランドから、おしゃれで人気のブランドの紹介
- 木のまな板を選ぶ際のポイント
木のまな板が持つメリットとデメリットを理解し、適切な手入れを行うことで、長く愛用できることを目指します。
- 木のまな板にカビや黒ずみが発生する原因と正しい予防策
- 自宅でできる具体的なカビ・黒ずみ除去方法と注意点
- 素材別のお手入れポイントとまな板を長く使うためのコツ
- まな板の選び方から買い替えのサインまで総合的な知識
≫より詳しく、木のまな板のカビや黒ずみ対策について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
木のまな板の魅力とカビ・黒ずみ対策の基本と効果的な落とし方
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ大切な木のまな板にカビや黒ずみを見つけてしまったとき、どのように対処すれば良いのでしょうか
この章では、まな板のトラブルを未然に防ぐ日々の習慣から、もしカビや黒ずみが発生してしまった場合の具体的な解決策まで、木のまな板を清潔に保つための基本と効果的なアプローチを詳しく解説していきます。
素材ごとの特性を理解し、適切な手入れを実践するためのヒントを見つけていきましょう。
- 使用前の「ひと手間」がまな板を守る
- 素材で変わるお手入れのポイント
- 重曹とクエン酸を活用したカビの取り方
- 頑固な汚れへの対処法
- まな板を削る?自分でできる範囲と専門サービスの活用
- ハイターは危険!変色のリスクと代替案
- 除菌スプレーのおすすめと効果的な使い方
- 手入れにはオイルを使って長持ちさせよう
使用前の「ひと手間」がまな板を守る
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージまな板を使用する前には、必ず全体を軽く水で濡らすようにしてください。これは、食材の匂いや色、油、そして水分が木材の内部に深く染み込むのを防ぐための昔ながらの知恵です。
とくに、食材の水分が木材に染み込むことは、カビの発生の主要な原因となるといわれています。
水で木の繊維を飽和させることで、食材から出る水分や色素、油分がそれ以上内部に深く浸透するのを防ぐ「水のバリア」を形成します。
これは、汚れてから対処する「反応的な清掃」ではなく、汚れの発生を未然に防ぐ「能動的な予防」であり、衛生的に使い始めるための、とても大切な一歩です。
水で濡らした後は、布巾で水気をおおまかに拭き取ってから切り始めると良いでしょう。完全に拭き取る必要はありません。
素材で変わるお手入れのポイント
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージまな板は使われている木材の種類によって、適切なお手入れ方法が異なります。
ご自身のまな板がどのような素材でできているか理解することが、長持ちさせる鍵となります。
オイルケアの要否
ヒノキやヒバのような国産の針葉樹材は、もともと油分を豊富に含んでいるため、使い始めにオイルを塗る「オイルフィニッシュ」は基本的に不要です。
一方で、竹製のまな板や、チーク・アカシアといった海外産のカッティングボードの中には、油分が少ないものも存在します。
これらの素材は乾燥によるひび割れや反りを防ぐため、また汚れの浸透を防ぐために、定期的なオイルケア(シーズニング)が推奨される場合があります。
ミネラルオイルや亜麻仁油など、食品に安全なオイルを選び、薄く塗布して浸透させ、余分な油は拭き取ることが大切です。
オイルを使ったお手入れの方法については、後述します。
抗菌性と匂い移り
ヒノキやヒバには、天然の抗菌成分が含まれており、雑菌の繁殖を抑える効果が期待できます。
そのため、日々の基本的な洗浄と乾燥をしっかり行っていれば、比較的衛生的に保ちやすいと考えられます。
イチョウは匂い移りが少ないという特性も持ち合わせていますが、抗菌作用はヒノキやヒバほど強力ではありません。
したがって、イチョウ製のまな板を使用している場合は、よりこまめな洗浄や、必要に応じた重曹や塩でのケアが必要です。
乾燥時の注意点
木材はどの素材も多孔質であり、水分を吸収しやすい性質を持っています。そのため、使用後の徹底した水気拭き取りと乾燥は、カビ予防において共通して非常に重要です。
とくにまな板の側面である木口は、木目に沿って水を吸い上げる管が通っているため、水分が残りやすく、カビの発生源となりやすい箇所です。
素材によっては、食洗機の使用や乾燥機の使用がひび割れや反りの原因となるため、製品の取扱説明書で対応しているか必ず確認してください。
記載がない場合は、手洗いと自然乾燥が基本で、食洗器は使用しない方が無難です。
≫まな板だけでなく、日々の調理器具の水切りにお悩みなら、こちらの記事も役立つかもしれません。
重曹とクエン酸を活用したカビの取り方
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ初期のカビや軽い黒ずみ、気になる臭いには、家庭にある身近な材料を使った方法が有効です。
ここで紹介する重曹とクエン酸を使用する方法は、木材に大きな負担をかけることなく、衛生状態の改善に役立ちます。
クエン酸スプレーの利用
まな板の臭いが気になるときや、軽く除菌したい場合にクエン酸スプレーは役立ちます。
強力な除菌や漂白効果は期待できませんが、木材に害を与えることなく細菌の繁殖を抑えるのに効果的です。
使用方法は、お湯200ccにクエン酸小さじ1を溶かしてスプレーボトルに入れ、まな板にキッチンペーパーを敷き、全体的にクエン酸スプレーを吹き付けます。
15分ほど放置した後、水拭きをしてしっかりと乾燥させてください。
重曹による洗浄
重曹は人体に無害で手肌への刺激も少ないため、掃除に適していると言えます。単体での漂白効果は強くありませんが、雑菌の繁殖を抑える静菌効果が期待できます。
使用方法まな板全体に重曹をまんべんなく振りかけ、スポンジやタワシで木目に沿ってやさしくこすり洗いすると良いでしょう。
重曹とクエン酸の組み合わせ
酸性のクエン酸とアルカリ性の重曹を混ぜると、化学反応で二酸化炭素の泡が勢いよく発生します。
この発泡作用を利用してカビ汚れを浮かせられ、赤カビや軽い黒カビであれば洗い流すことが可能だとされています。
具体的には、クエン酸スプレーをかけた箇所に重曹を歯ブラシにつけてこする方法が効果的です。
ただし、根を張った頑固な黒カビには効果が期待できません。あくまで初期のカビ取りや繁殖を抑える予防策として認識しておくことが大切です。
頑固な汚れへの対処法
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ軽いカビや黒ずみに対しては、前述の重曹やクエン酸が化学的な作用で汚れを浮かせるのに有効です。
しかし、さらにしつこい色素沈着や、包丁の傷に入り込んだ汚れには、物理的なアプローチが必要になることがあります。
レモンと塩の活用
レモンに含まれる酸は、まな板に残った色素汚れや水アカ汚れを分解するのに役立ちます。
それに加えて、粗塩をレモンの断面につけてまな板の表面を擦ることで、塩の持つ研磨作用が加わります。
この研磨作用は、重曹やクエン酸だけでは届きにくい、包丁の細かな傷の奥に溜まった汚れを物理的にかき出すのに効果を発揮するのです。
また、レモンや柑橘系の香りには脱臭効果もあり、まな板の嫌な匂いが気になるときにも適しているでしょう。
具体的な方法としては、レモン汁をまな板の一面にかけ1時間程度放置して洗うか、レモンの皮を使ってまな板を直接磨くこともできます。
粗塩をまな板にふりかけ、半分に切ったレモンでこするのも良い方法です。塩単体でも研磨効果があり、たわしでかき出すことで包丁の傷に溜まった汚れを落とせるでしょう。
また、塩の浸透圧による菌の脱水作用も期待できます。
熱湯消毒の適切なタイミング
肉や魚を切った後のまな板は、匂いやタンパク質汚れが気になります。しかし、汚れたまな板にいきなり熱湯をかけることは避けてください。
肉や魚に含まれるタンパク質は、熱湯によってまな板の表面で固着し、汚れが内部に入り込んでかえって取れにくくなってしまいます。
そのため、必ず水で汚れを洗い流してから、最後に殺菌のために熱湯を回しかけるようにしましょう。
熱湯消毒は一般的な家庭であれば週に1回程度、肉や魚を頻繁に調理する場合や梅雨時期・夏場などの湿度が高い季節には、2~3日に1回行うとカビ予防につながります。
まな板を削る?自分でできる範囲と専門サービスの活用
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ大切に使ってきた木のまな板に、もしも深い傷や頑固な黒ずみができてしまったら、どうしていますか?
この章では、そんなまな板を諦めることなく、新品のように蘇らせるための方法をご紹介します。
ご自身でできる簡単な削り方から、プロの技術に頼るべきケースまで、まな板の寿命を延ばし、安全で快適な使い心地を取り戻すための具体的な方法を詳しく見ていきましょう。
自分で削る方法(サンドペーパー)
軽度の黒ずみやカビ、まな板の小口(側面)の黒ずみであれば、サンドペーパーを使って自分で削ることが可能です。
-
STEP1まな板を削る準備目の粗いサンドペーパー(#100~#150程度)と、仕上げ用の細かいサンドペーパー(#240以上、表面をツルツルにするなら#800以上)を用意します。
-
STEP2木に紙やすりを巻く削る際は、積み木くらいの大きさの木に紙やすりを巻き、均一に力を加えやすく削りやすい状態にしてください。
-
STEP3削る黒カビのある箇所を中心に、まな板全体を均一にやさしく削ります。へこんだ部分をなくすように、全体を平らにすることを意識しましょう。
-
STEP4なめらかに仕上げるカビや黒ずみが落ちたら、徐々に目の細かいサンドペーパーに変えていき、表面をなめらかに仕上げます。
-
STEP5側面も削る小口(側面)の黒ずみも同様にサンドペーパーで削りましょう。
-
STEP6洗浄削った後は、必ず中性洗剤とスポンジ(またはタワシ)でまな板全体をしっかり洗浄し、水気を拭き取って十分に乾燥させてください。
-
STEP7仕上げはオイルでその後、木のまな板用のオイルでケアすると良いでしょう。
カビが木材の内部まで深く浸透している場合は、削るだけでは完全に除去できない可能性があります。
ヤスリで研磨した後は、表面がザラザラになったり毛羽立ったりすることがありますが、使用後にたわしなどでしっかりと洗っていれば徐々になくなるでしょう。
また、広範囲を均一に平らに削るのは根気が要り、素人には難しい作業です。削りすぎると厚みが減って安定感がなくなるため、慎重に行わなくてはなりません。
自力では難しいと感じている方は、専門サービスの頼むのも一つの手です。専業者によるまな板の削りなおしについては、次の章で解説します。
≫包丁のサビや汚れも気になりませんか?自宅でできる簡単な手入れ方法をこちらの記事で解説しています。
専門サービス利用のすすめ
自分で削ることが難しい場合や、カビの範囲が広くて深い場合、は、専門業者に依頼するのが最も確実で安心な方法です。
まな板を購入した店舗や、木材店・工務店・包丁屋(鍛冶屋)・調理道具を扱う専門店・デパート・百貨店などで、削り直しサービスを受け付けていることがあります。
近くに店舗がない場合でも、宅配でまな板を送って削り直しを依頼できるサービスも存在します。
費用はまな板のサイズや状態によって異なりますが、家庭用まな板であれば1枚あたり数千円が目安です。
持ち込みであれば15分程度でその場で削り直してくれる場合もありますが、宅配サービスでは1〜2か月程度の納期がかかることもあるため、事前に確認することをおすすめします。
一部のメーカーでは、自社製品の削り直しを無料で行っている場合もあるため、お手持ちのまな板のメーカーに確認してみるのも良いでしょう。
ハイターは危険!変色のリスクと代替案
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ木のまな板に漂白剤(キッチンハイターなど)を使用することは、基本的におすすめできません。
自然素材である木材には薬品に対する耐性がなく、漂白剤を使うと黒ずみや変色を起こす恐れがあります。
また、漂白剤の使用は、変色や変形の原因となるだけでなく、漂白剤で傷んだ部分からさらに黒ずみやカビが発生する恐れもあるのです。
さらに、薬剤が木材に染み込むことにより、食材への影響も懸念されます。漂白剤がプラスチックまな板には有効であるのに対し、多孔質で有機物である木材とは根本的に相性が悪いいといえるでしょう。
やむを得ない場合の注意点
そもそも木製まな板への漂白剤の使用は、種類を問わず木材の劣化や食材への影響が懸念されるため、推奨されません。
泡タイプの漂白剤であっても、特定の箇所に強力に密着することで薬剤が深く浸透し、すすぎ残しのリスクや部分的な変色の恐れがあるため、使用は避けてください。
もし漂白剤を木製まな板に使用せざるを得ない場合は、必ず製品の説明書通りに希釈し、短時間(ごくわずかな時間)のみの使用に留めることが大切です。
また、長時間浸け置きすることは避け、使用後は中性洗剤で洗浄し、流水で念入りにすすぎを行ってください。
塩素系漂白剤は皮膚を傷める可能性があるため、必ずビニール手袋などを装着して作業しましょう。
繰り返しますが、木のまな板に漂白剤を使うことは、基本的に避けるべき方法です。
洗浄は漂白剤以外の方法で
木製まな板の黒ずみやカビの色素はまな板の内部に浸透していることが多く、漂白剤でも完全にきれいにするのは難しいでしょう。
代わりに、前述のクエン酸スプレーや、レモンと粗塩を使った方法など、より木材にやさしい方法を検討することをおすすめします。
次章では、除菌スプレーを使った洗浄方法を紹介します。
除菌スプレーのおすすめと効果的な使い方
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージまな板の衛生を保つためには、日々の洗浄に加えて定期的な除菌が重要です。
市販の除菌スプレーにはさまざまな種類があり、それぞれの特性を理解して適切に使い分けることが効果的な衛生管理につながります。
アルコール系除菌スプレー
消毒にも使われるアルコールは、極めて高い除菌効果を持ち、多くの雑菌やウイルス(エンベロープウイルス)を死滅させるとされています。
アルコールで除菌することで、まな板などの気になる臭いを消臭する効果も期待できるでしょう。
市販のアルコール系除菌スプレーは、100%食品・食品添加物原料の製品が多く、食器にかかっても安心で、拭き取りや水洗い不要なものもあります。
まな板・調理器具シンク・食卓・冷蔵庫などの除菌に幅広く使えますが、汚れに対する洗浄力はそれほど高くないため、除菌が主な目的となります。
アルコール消毒液に長時間漬けると腐食が発生する可能性がありますが、スプレーで吹きかけて消毒する程度であれば問題ありません。揮発性が高いため、拭き取る必要がない製品も多いです。
次亜塩素酸水
次亜塩素酸を主な成分とした酸性の溶液で、その酸化作用によって細菌やウイルスを除菌します。インフルエンザウイルスやノロウイルスの除菌にも、高い効果が期待できます。
次亜塩素酸水は、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤の主成分)とは別物です。また、有機物と反応すると分解されて水に戻る性質があるため、人体への影響は少ないとされています。
口に入るものへの使用は推奨されておらず、手指の消毒にも安全性が確認されていないため、物の除菌のみに使用するのが推奨されます。
塩素に過敏な人は使用を控え、濃度に注意し、酸性タイプの洗剤と混ぜないようにしましょう(有毒な塩素ガスが発生する危険性があるためです)。
紫外線で分解されやすいため、遮光ボトルに入れて冷暗所に保管し、早めに使い切る必要があります。
木製まな板に次亜塩素酸水を使用すると、変色や変形の原因となることもあります。ただし、洗浄剤を木材に浸透させ、汚れのもとを浮き出させてから水で流す方法であれば、木材を傷める心配は少ないでしょう。
アルカリ電解水
水を電気分解して作られるアルカリ性の溶液で、添加物を含まず、原料は水です。
高い除菌効果を持ち、アルコールでは太刀打ちできなかったノンエンベロープウイルス(ノロウイルスなど)の不活化も、可能とされています。
水に濡れた場所でも薄まることなく高い除菌効果を発揮します。99%以上が水でできているため、肌荒れを引き起こす不安が少なく、初めて除菌スプレーを使う人にも適しているといえるでしょう。
食べ物を扱うキッチンでも安心して使えるとされています。除菌や消臭だけでなく、洗浄力にも優れているため、手垢や油汚れなどの掃除にも使えます。
家庭で発生する汚れの大半を落とせるため、常備しておくと重宝するでしょう。アルコールや塩素系漂白剤のような独特の臭いがしないため、臭いに敏感な人にもおすすめです。
出典:
東京ガスのハウスクリーニング
厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」
手入れにはオイルを使って長持ちさせよう
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージオイルを使った手入れは、木のまな板の寿命を延ばす上で非常に重要です。オイルは木の水分を適切に保ち、乾燥による反りや割れを防ぎます。また、木目の自然な美しさを引き立て、まな板を新品のように美しく保つ効果もあります。
さらに、表面を保護することで、カビが生えにくくなり、汚れもつきにくくなるという衛生的な効果も期待できるでしょう。
オイル塗布の目的は単に「木目の美しさを引き立てる」という美的側面だけでなく、木材が乾燥しすぎたり水分を吸いすぎたりするのを防ぐ「水分調整剤」のような働きをします。
つまり、まな板が反ったり割れたりするのを防ぎ、さらにカビが生えにくい衛生的な状態を保つための、とても大切な特別なケアといえるのです。
適切なオイルの選び方
まな板に使用するオイルは、食品に触れても安全なものを選ぶのが最も大切です。
食器やカトラリーには、食品や口に触れても安心な植物性オイルがおすすめですよ。とくにまな板やお皿などには、食品衛生の観点から純度の高い天然オイルを選ぶと安心できるでしょう。
いくつかあるオイルの種類と、その特徴を下の表にまとめました。
| オイルの種類 | 特徴 |
| 乾性油 |
|
| ミネラルオイル |
|
| オリーブオイル |
|
| ワックスクリーム |
|
選ぶ際の注意点として、クルミ油などのナッツ由来のオイルは、ナッツアレルギーを持つ人がアレルギー反応を起こす恐れがあります。
ご家族にアレルギーのある方がいる場合は、使用前に必ず確認するようにしましょう。
オイル塗布の頻度と方法
新しい木製まな板を手に入れたら、最初に油を塗ることが重要です。これは木材に油を染み込ませることで、水分の吸収を防ぎ、カビや割れを防ぐ目的です。
ただし、オイルの塗布頻度は、まな板の素材や使用頻度によって異なります。国産針葉樹材(ヒノキ、ヒバなど)はもともと油分が豊富なので、基本的に最初にオイルフィニッシュをする必要はありません。
最初に塗布(ヒノキ、ヒバ以外)して以降の一般的な目安としては、まな板が「カサカサしてきたな」と感じたら塗るのが良いでしょう。月に1度程度のディープクリーニングと合わせて行うのがおすすめです。
定期的な手入れとして年に1〜2回、または年に2〜3回の頻度でオイルの塗り直しを行うことが推奨されています。
塗布する際はまな板が完全に乾いていることを確認し、表面の汚れを徹底的に落としてください。
そして、柔らかく清潔な布にたっぷりとオイルを含ませ、木目に沿って丁寧に擦り込むように塗布します。
オイルの量は、木が飽和する程度で、油っぽくならない程度にするのがポイントです。オイルを数時間から一晩置いて、木の中心部まで浸透させます。
浸透後、余分なオイルは清潔な布で拭き取ってください。オイルを塗った後にボードクリームを塗ると、天然のワックスがさらなる保護バリアとなるでしょう。
木のまな板 カビ・黒ずみ 落とし方と長持ちさせるケア
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ木のまな板との付き合い方がわかると、調理がもっと楽しくなります。
この章では、木のまな板が持つ本来の魅力から、寿命が来た際のサイン、そしてもし買い替えるならどのようなまな板を選べば良いのかまで、長く愛用するための実践的な知識をご紹介します。
あなたのキッチンにぴったりの一枚を見つけ、快適な調理環境を整えるためのヒントを見つけていきましょう。
- デメリット メリットを理解する
- そろそろ寿命?見落としがちな買い替えのサイン
- カビない人気素材と選ぶポイントを解説
- 無印 ニトリのおすすめを紹介
- おしゃれなブランドでワンランク上のキッチンに
デメリット メリットを理解する
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ木のまな板を選ぶ際には、プラスチック製やゴム製にはない独自の魅力と、適切に付き合うための注意点を理解しておくことが大切です。
メリット
木のまな板の最大の利点は、包丁の刃へのやさしさにあります。
木材は適度な柔らかさで包丁の刃を受け止めるため、刃が傷つきにくく、切れ味が長持ちするといわれています。
何より「トントントン」という軽やかなカット音は、調理の時間をより心地よいものに変えてくれるでしょう。
また、木のまな板は適切に手入れをすれば非常に長く使用できる、エコフレンドリーな選択肢です。
表面が摩耗したり黒ずんだりしても、カンナで削り直したり、オイルで定期的に手入れをすれば、新品同様に再生させられるでしょう。
とくにホオノキやヒノキのような木材は、3~4年に一度の削り直しで20年以上現役で使い続けられるといわれており、その持続可能性は特筆すべき点です。
一部の木材、例えばヒノキやヒバなどは、天然の抗菌成分を含んでいるため、雑菌の繁殖を抑える効果が期待できます。
デメリット
一方で、木のまな板にはいくつかの課題も存在します。最も大きな懸念は衛生管理の難しさです。
木のまな板は包丁の刃によって細かな傷が無数につきやすく、その傷の隙間に食材のカスや水分が入り込み、細菌や黒カビが繁殖しやすい環境を作り出します。
また、木材自体が有機物であるため、カビの栄養源となりやすい性質も持ち合わせています。
さらに、吸水性が高いため、使用後の乾燥に時間がかかる点もデメリットです。表面が乾いて見えても、木材の内部には水分が残っていることがあり、これがカビの温床となることがあるのです。
また、急激な乾燥や直射日光への長時間露出は、まな板の割れや反りの原因となるため、保管方法にも注意してください。
素材によっては重さがあり、持ち運びや取り扱いが大変に感じる場合もあるでしょう。木のまな板の「長寿命」という利点は、単に素材が丈夫であることだけでは実現しません。
木材の多孔質性という物理的特性を理解し、ユーザーが適切な手入れと必要に応じた削り直しを継続的に行うことによって初めて、その真価が発揮されます。
つまり、「手入れをすれば高いリターンが得られる」特性を持つ調理器具と言えるでしょう。
そろそろ寿命?見落としがちな買い替えのサイン
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ木のまな板は適切に手入れすれば長く使えますが、それでも寿命は存在します。
以下のようなサインが見られた場合は、衛生面や使用上の安全性を考慮し、買い替えを検討することが大切です。
買い替えのサイン
- 黒カビが木の内部まで浸透している:
洗剤や削り直しを試しても、黒カビの色素が木の奥深くまで染み込んでしまい、完全に除去できない場合です。
見た目だけでなく、衛生面でも雑菌の繁殖や、それが食材に移行する可能性が懸念されます。 - ひどい反りや割れ:
まな板が大きく反ってガタついたり、深い割れが入ったりしている場合、安全に食材を切ることが難しくなります。
反りがひどいと包丁の刃がまな板に均一に当たらず、切り残しが出たり、包丁の刃こぼれの原因になったりします。 - 目立つへこみや深い傷:
包丁によるへこみや傷が深くなり表面がでこぼこしていると、食材のカスが溜まりやすくなり、衛生的に保つのが困難になります。
また、切り心地も悪くなります。 - 不快な臭いが取れない:
どれだけ洗浄や除菌をしても、まな板からいつまでも嫌な臭いが取れない場合、雑菌が奥深くで繁殖している可能性があります。
買い替えを怠るとどうなる?
カビや黒ずみが深く浸透したり、まな板が劣化したりした状態で使用を続けると、以下のようなリスクが生じます。
- 食中毒のリスク:
まな板に深く刻まれた傷や木材の奥にまで根を張ったカビ、洗浄しきれない食材の残りカスなどは、雑菌や食中毒菌の温床です。
目に見えない菌が別の食材(とくに生食するもの)に移る「二次汚染」を引き起こし、食中毒の原因となる可能性があります。
カビの中には人体に有害な物質を生成するものもあり、食材を通じて摂取するリスクも考えられます。 - 衛生面での不快感:
黒ずみやカビ、嫌な臭いが定着したまな板は、見た目にも衛生的ではなく、調理へのモチベーションを低下させます。 - 調理効率の低下と怪我の危険:
反りやひび割れが生じたまな板は安定性が悪くなり、食材が切りにくくなります。
包丁の刃当たりも悪化し、スムーズな調理を妨げ、思わぬ怪我につながる可能性も出てきます。 - 耐久性の低下と破損:
劣化が進んだまな板は、強度も落ちています。
使用中に割れたり、欠けたりするリスクが高まり、安全に使用できなくなることがあります。
一般的に、木製まな板の寿命は5~7年程度とされていますが、これはあくまで目安です。
日々の手入れや使用頻度によって大きく変わりますので、上記のサインが見られたら、積極的に買い替えを検討することをおすすめします。
カビない人気素材と選ぶポイントを解説
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ木のまな板を選ぶ際、カビにくさや使い心地は重要なポイントとなります。ここでは、人気のある素材とその特性、そして選ぶ際のポイントを解説します。
まな板の素材とその特性
ヒノキ (桧)
適度な堅さと優れた耐水性を持つ、まな板の定番素材です。
αカジノールやヒノキオールといった天然の抗菌成分を含み、雑菌の繁殖を抑え、抗菌・消臭効果が期待できます。
刃当たりが良く、長時間の調理でも手や腕への負担を軽減すると評判です。ヒノキ特有の清々しい香りにはリラックス効果がありますが、香りに敏感な人には強く感じられるようです。
国産のヒノキはもともと油分が豊富であるため、使い始めにオイルフィニッシュをする必要は基本的にありません。速乾性にも優れています。
ヒバ (檜葉)
とくに青森ヒバは、日本三大美林の一つに数えられ、ヒノキチオールという強力な抗菌成分を含んでいます。そのため、抗菌・防カビ・防虫効果が非常に高く、衛生的に使用できるのが最大の利点です。
耐久性に優れ、水に強く腐りにくい性質を持つため、長く愛用できる素材です。
ヒバの香りにもリラックス効果がありますが、独特の香りを苦手とする人もいます。希少価値が高いため、価格も比較的高価な傾向があります。
イチョウ (銀杏)
適度な柔らかさと均一な木質が特徴で、包丁の刃当たりが非常に良く、刃を傷めにくいと多くの料理人に愛用されています。
適度な油分を含むため水はけが良く、乾燥が早いことから衛生的に使用できるでしょう。抗菌作用も持ち合わせており、カビが生えにくい特性も持ち合わせているといわれています。
匂い移りが少ないため、刺身など香りに敏感な食材を扱う際にも好相性です。
竹 (バンブー)
成長が早く、農薬や化学肥料を必要としないエコ素材として近年注目されています。抗菌性があり、まな板を清潔に保つのに適しているでしょう。
軽量で扱いやすく、硬さも適度で包丁の刃を傷つけにくい特徴があります。
使用前にシーズニング(油を塗って乾燥させる処理)を行い、洗剤での洗浄を避けるなど、適切なメンテナンスが必要です。
比較:木製・ゴム製・プラスチック製
まな板には木製のほかにも、ゴム製やプラスチック製などさまざまな種類があります。
それぞれの素材が持つ特性を理解することで、ご自身の調理スタイルや重視するポイントに合った最適なまな板を見つけられるでしょう。
下の表では、それぞれの素材が持つ特徴を比較しています。
| 素材の種類 | 特徴(カビにくさ・お手入れ) | 刃当たり・その他 |
| 木製 |
|
|
| ゴム製 |
|
|
| プラスチック製 |
|
|
無印 ニトリのおすすめを紹介
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ手軽に入手できるブランドとして、無印良品とニトリのまな板も人気を集めています。
これらのブランドは、手の届きやすい価格帯でありながら、日常使いに適した機能性とデザインを提供しています。
無印良品
無印良品では、日々の調理に手軽に取り入れられる、シンプルで機能的なまな板が揃っています。
ひのき調理板・薄型・大
手軽に使える木製まな板を探している方におすすめします。包丁が当たる感覚はやや硬めですが、カット音は響きにくく、切り心地は良好との評判です。
人参を切った後も深い傷や色移りが残りにくく、使用感が出にくいのが特徴です。水切れにも優れ、濡らしてから2時間で表面がサラッとした状態になるとの報告もあります。
国産天然ヒノキを使用しており、抗菌・消臭効果のあるαカジノールが含まれるため、カビやニオイの抑制も期待できます。
また、シンプルでキッチンになじみやすいデザインも好印象です。
Ag+抗菌加工 やわらかいまな板
薄くて柔らかいのに切りやすく、包丁の刃が滑りにくいのが特徴です。肉と野菜で使い分けられる両面仕様(「Vegetable」「Meat」表示つき)で衛生的です。
薄型で場所を取らず、丸めて収納できるため、キャンプなどのアウトドア用途にも適しているでしょう。
ただし、耐熱温度が60℃と低く、熱湯消毒や食洗機には対応していないため注意が必要です。
ニトリ
ニトリは幅広い種類のまな板を取り揃えており、価格の手頃さも魅力です。
食洗機対応 ひのきまな板
食洗機に対応したヒノキ製のまな板で、手入れのしやすさを重視する方におすすめです。
軽量ひのきまな板
水に強く、傷がつきにくいヒノキを使用しながら、重さ400gと超軽量なタイプも提供されています。包丁への当たりがやさしく、食材が滑りにくいためスムーズにカットできます。使うたびにヒノキ特有の香りが楽しめるのも魅力です。
アカシア・マホガニー製カッティングボード
おしゃれな木製カッティングボードとして、風合いのあるアカシアやマホガニー素材の製品も提供しています。
切れ味感動 魔法のまな板
合成ゴム素材でできており、弾力性があるため包丁の刃こぼれしにくく、傷にも強いのが特徴です。
コンパクトなサイズで、食材の水分を排出するスリットやこぼれを防ぐ溝など、便利な機能も備えています。
おしゃれなブランドでワンランク上のキッチンに
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ機能性だけでなく、見た目の美しさも重視したい方のために、おしゃれで機能的なまな板ブランドと製品をいくつか紹介します。これらのまな板は、キッチンを彩るだけでなく、調理のモチベーションも高めてくれるでしょう。
WONDER WOOD MANAITA 贈るまな板
樹齢100年以上のイチョウの木を使用した上質なまな板です。
抗菌性、耐水性、耐久性が高く、握りやすい曲面加工が施されています。ギフトにも適しているでしょう。
ヤマコー ひのき まな板ボード(はぎ合わせ)
国産ヒノキを使用し、天然木のナチュラル感が魅力です。曲線的な形状と丸みのあるサイドがおしゃれな印象を与えます。耐水性が高く丈夫で、ヒノキの香りに癒されるとされています。
梅沢木材工芸社 浮かせて使える青森ひばのまな板
両脇の丸い桟により、使用中に裏面が浮いた状態になるため衛生的です。
両面使用可能で、立てて収納できるのも特徴です。
ウッドペッカー (woodpecker)いちょうの木のまな板
岐阜県発の日本のブランドです。質の良い国産イチョウの一枚板から作られたまな板は、程良い弾力で刃当たりがやさしく、長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
GLOBALカッティングボード
オールステンレス包丁で有名なGLOBALのヒノキ製まな板です。
表面にシリコン樹脂塗装が施されており、撥水性に優れ傷つきにくいとされています。
ラバーゼ (la base)
イタリア語で「基本」を意味する日本のブランドです。使いやすさ、美しさ、耐久性にこだわった上質なキッチン用具を手掛けています。硬すぎず柔らかすぎないゴムの木が使われており、刃当たりが良いと評判です。
アルテレニョ (Arte Legno) カッティングボード オリーブ無垢材
イタリアのブランドで、厳選されたオリーブウッドを使ったまな板が特徴です
。熟練職人の手作業で生み出され、一つずつ木目や形状が異なるため、一点物のおしゃれなアイテムを求める人におすすめです。
木のまな板のカビ・黒ずみ落とし方【まとめ】
 刃音録ーイメージ
刃音録ーイメージ木のまな板のカビや黒ずみを防ぐには、使う前のひと手間と、使った後の徹底した洗浄・乾燥が重要です。
万が一カビが発生しても、重曹やレモンと塩、あるいは削り直しで対処できますが、漂白剤の使用は避けましょう。
また、まな板の寿命や買い替えのサインを理解し、素材ごとの特性を知ることで、あなたのキッチンに最適な一枚を選べます。
今回ご紹介したお手入れ方法と選び方を参考に、ぜひ今日から実践して、木のまな板を清潔に保ち、より快適な調理時間を手に入れてください。
- 木のまな板は温かみや刃へのやさしさなど多くのメリットがある
- カビや黒ずみの主な原因は木の繊維に入り込む水分と食材カスである
- 使用前の水濡らしは食材の匂いや汚れの染み込みを防ぐ大切な予防策である
- 使用後はすぐにタワシで木の目に沿って洗い、水気を徹底的に拭き取ること
- 乾燥は風通しの良い日陰で立てて行うことがカビ予防につながる
- 肉や魚を切った後は、まず水で洗い、最後に熱湯消毒を行う
- 軽度のカビには重曹やクエン酸、レモンと塩を使った方法が有効である
- 根深いカビやへこみにはサンドペーパーで削る物理的な除去が効果的である
- 自分で削るのが難しい場合は専門業者による削り直しサービスを検討すると良い
- 塩素系漂白剤は木材の変色や劣化を招く恐れがあるため使用を避けるべきである
- 除菌スプレーはアルコール、次亜塩素酸水、アルカリ電解水の中から目的に合わせて選ぶ
- オイルケアはまな板の反りや割れを防ぎ、美しさと衛生を保つ重要なスペシャルケアである
- まな板の素材によってオイルケアの必要性やお手入れのポイントが異なるため注意する
- 黒カビが浸透したり、反りや割れがひどい場合は衛生面から買い替えを検討することが大切である
- 木のまな板を長く使うためには日々の丁寧な手入れと、素材に合わせたケアが鍵となる
「すぐ焦げ付く」「どれがいいか分からない」…そんな悩みから卒業しませんか?
素材選びから寿命の判断、正しい手入れまで。フライパンに関するあらゆる疑問の答えをここに凝縮しました。